本連載は、物流業における人材確保及び将来の物流という観点から、過去の裁判例を解説するものです。
令和7年6月1日、労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策を講じることが義務として規定されました。これまでも、報告体制や応急措置に関し努力義務として規定されてきましたが、今回、罰則を伴う法的義務となったのです。
近年、猛暑の影響により物流現場の職場環境は著しく悪化しています。実際に、職場における熱中症の発生件数は急増しています。他の業種と比較しても、建設業、製造業、そして物流業では、熱中症の発生件数は多く、大きな問題となっています。厚生労働省が発表した「2024年(令和6年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」では、職場における熱中症による死傷者数が、2015年に464人だったところ2024年には1257人と3倍に近づく勢いで増加しています。また、業種別の状況を見ると、2024年の死傷者1257人の内、建設業が228人、製造業が235人、運送業が186人となっていますし、運送業はもう何年も死傷者数上位にいます。運送業の現場では熱中症による死傷のリスクが非常に高いといえます。
また、熱中症による死傷者数の年齢別の状況(2024年の全業種)をみると、20~24歳では68人であるのに比べ、55~59歳では177人と2.5倍以上になっています。加齢によって熱中症のリスクが高くなっていくと考えられます。運送業では近年、従事者の高齢化は避けられない状況ですから、このような観点からも、運送業における熱中症対策は他の業種に比べて取り組むべき重要課題です。
実は私も企業で勤務していた頃には物流の現場で仕事をすることもありました。真夏の倉庫で積込みや荷卸しをしたときには、倒れそうになったのを思い出します。
さて、今回は、熱中症対策を講じることが義務であるのに、対策を講じなかった結果、従業員が熱中症により倒れてしまったとしたら、事業者は責任を負うのかについて考えてみたいと思います。
今回取り上げる事案は、いわゆる安全配慮義務に関する裁判例(最判平成3年4月11日集民162号295頁)です。熱中症の事案ではありませんが、事業者が労働環境に関しどこまで義務を負うのかについて考えさせられる事案です。では事案をみていきましょう。
AらはB社の造船所に勤務していました。Aらの中にはB社の従業員もいましたし、B社の従業員ではなく下請け企業の従業員もいました。Aらは、造船所の騒音によって難聴障害となったとしてB社に損害賠償を求めたのでした。最高裁は、結論として、B社は下請け企業の労働者についても損害賠償責任を負うと判断しました。最高裁は、下請企業の労働者がB社の造船所で労務の提供をするに当たっては、いわゆる社外工として、B社の管理する設備、工具等を用い、事実上B社の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容もB社の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり、このような事実関係の下においては、B社は、下請け企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対して安全配慮義務を負うと判断しました。
安全配慮義務は、労働者が労務提供の為設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮する義務と定義されてきました。事業者がこの安全配慮義務に違反して労働者に疾病等が生じた場合、事業者はその損害を賠償する責任を負うこととなります。事業者は、労働者が労務提供するにあたって直面する身体の危険等から労働者を守らなければならないのです。事業者はあらゆる危険を想定して対策しておくべきと言っても過言ではありません。
近年では、労働者が過重な業務に従事したことで精神障害を発症した場合に事業者が責任を負うべきとして損害賠償請求される事案、石綿による中皮腫について事業者が責任を負うべきとした裁判例等があり、そのほかにも多くの安全配慮義務に関する事案がみられます。もちろん、安全配慮義務の範囲には、職場における熱中症対策も含まれてきます。
今回取り上げた裁判例では、事業者は、直接の雇用関係にある労働者に対してだけでなく、直接の雇用関係にはないが一定の関係にある労働者に対しても、安全配慮義務を負うとしました。事業者は、労働者の労働環境について広く責任を負うのだと認識しておかなければなりません。
さて、熱中症対策の話に戻ります。上述のように、過去の実績から、物流業の現場では熱中症のリスクが非常に高いと言えます。そして、今回の改正では事業者に熱中症対策が義務付けられました。事業者は、現場で熱中症リスクが高いと認識しうる状況ですし、対策を講じなければならないのは法令上で定められました。今後は、事業者が何の対策もせずに現場で熱中症が発生した場合、事業者はその責任を問われるでしょう。事業者として、可能な限りの対策を講じていくべきです。物流の現場が、労働者の健康維持に配慮された職場へと変わっていき、十分な人材が確保できる業界になっていくことを願っています。
9月1日 熱中症対策【今日のコラム】
 未分類
未分類

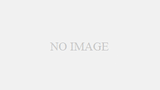
コメント